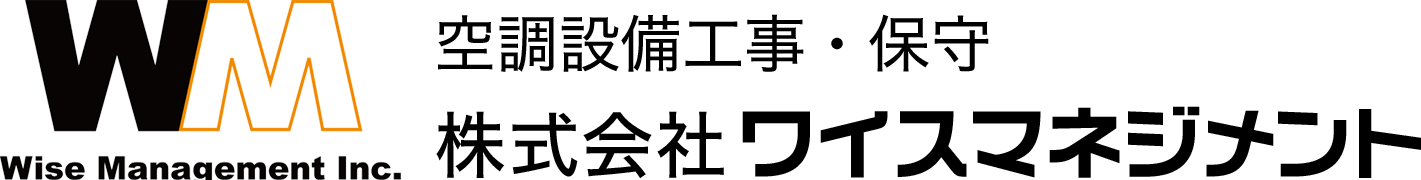今日は建国記念の日です。

「建国記念の日」は、日本の国が成立したことをお祝いする日です。 この祝日の起源や、なぜ2月11日になったのかについて。お話ししたいと思います。
「建国記念の日」は、もともと戦前に存在した「紀元節(きげんせつ)」が由来です。 紀元節は、初代天皇とされる神武天皇が即位したとされる日(紀元前660年2月11日)を記念する日でした。 しかし、戦後のGHQ(連合国軍総司令部)の占領政策の一環で1948年に廃止されました。 その後、国民の要望によって1966年に「建国記念の日」として新たに制定されました。
「建国記念の日」が正式に制定されたのは1966年(昭和41年)で、翌1967年から祝日として施行されました。
そのルーツをたどると、日本書紀に記された神武天皇の即位の日に由来します。 神話上の出来事ではありますが、長年にわたり日本の歴史と文化に根付いてきた日として、今も祝日として存在しています。
建国記念の日(けんこくきねんのひ)は、日本の国民の祝日の一つ。
国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条は、建国記念の日の趣旨について、「建国をしのび、国を愛する心を養う。」と規定している。1966年(昭和41年)の祝日法改正により国民の祝日に加えられ、翌1967年(昭和42年)2月11日(政令により規定)から適用された。
制定
[編集]
世界で「建国記念日」を法律で定めて祝日とする国家は多いが、何をもって建国記念日とするかは、国によって異なる。日本では、建国の日が明確ではないが、建国をしのぶ日として法律に基づき「建国記念の日」が定められた。日付は政令に基づき、日本神話を基に建国日とされていた紀元節(1948年(昭和23年)7月、祝日法制定に際し廃止[1])と同じ2月11日にされた。
2月11日は、神武天皇(日本神話の登場人物であり、古事記や日本書紀で初代天皇とされる)の日本書紀における即位日(辛酉年春正月、庚辰朔、すなわち、旧暦1月1日〈『日本書紀』卷第三、神武紀 「辛酉年春正月 庚辰朔 天皇即帝位於橿原宮」〉)の月日を、明治時代にグレゴリオ暦での具体的な日付として推定したものである[注 1]。
法令上の位置づけ
[編集]
他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、本日のみが「政令で定める日」と定められている(経緯は#沿革を参照)。この規定に基づき、佐藤内閣が建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)を定め、「建国記念の日は、二月十一日」とした。
紀元節(きげんせつ)は、古事記や日本書紀で日本の初代天皇とされる神武天皇の即位日をもって定めた祝日。日付は紀元前660年2月11日。1873年(明治6年)に定められた。かつての祝祭日の中の四大節の一つ[1]。
1948年7月20日の「国民の祝日に関する法律」公布・施行により、紀元節を含む四大節は廃止された[2]。1966年(昭和41年)に同じ2月11日が「建国記念の日」として国民の祝日となり、翌年から適用された。
2月11日の日付は、日本書紀で神武天皇が即位したとされる神武天皇元年(紀元前660年)1月1日の月日を、明治に入りグレゴリオ暦に換算したものである。
この日は、全国で「建国記念の日」を考える集会が開かれます。
本当に国民にとりまして大事な日です。何とか元の紀元節に名称を変えたいです。